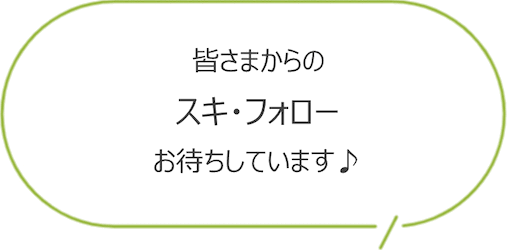がんにかかったら出産は難しいの?治療前に医師と話しておきたい妊よう性のこと【FP黒田の人生相談】
がんにかかったらもう子どもが産めなくなるの? そんな相談を寄せてくれたのは、31歳の女性。
実は、がんの治療によって生殖機能に影響が出る可能性もあります。国立がん研究センターがん情報サービスのウェブサイトには、次のように書かれています。
『がんの治療の進歩によって、多くの若い患者さんもがんを克服できるようになってきています。そして近年では、将来自分の子どもをもつ可能性を残すために、卵子や精子、受精卵を凍結保存する「妊よう性温存」という選択肢も加わってきました。まずは、がんの治療を受けることが大前提ですので、必ずしも希望通りにならない場合もありますが、将来子どもをもつことを望むのか、治療前に考えてみることも大切です。』
がんと告知を受けた後でも、子どもが欲しいと思ったら、まずは何から始めたら良いのでしょうか。その方法やかかる費用は? 黒田先生がお答えします。
【相談】
先日TVで子宮頸がんに関するニュースを見ていて、ふと「がんにかかったら子どもが産めなくなるのかもしれない……」と不安になりました。その後、自分で調べてみたところ、子どもを諦めずに済むこともあるとか。それって本当なのでしょうか。がんの治療費のほかに、どのくらい費用が必要になるのかも気になります。黒田先生、教えてください!(31歳・女性)
がん治療と妊よう性をどう両立させるか
「妊よう性」という言葉を聞かれたことはありますか? これは、「妊娠できる能力」を指します。
妊娠するためには、女性なら卵巣や子宮、男性なら精巣などの生殖機能が必要ですよね。
妊娠するための妊よう性をいかに保つかは、男女ともに重要な問題です。

妊よう性は加齢とともに低下します。特に女性の場合、35歳を境として、顕著に妊娠する確率が減っていくといわれています。
晩婚化・晩産化が進んでいることもあり、不妊治療を受けている夫婦はいまや珍しくありませんが、問題は、若い年代の女性でも子宮頸がんや乳がんなどのがん罹患率が上昇していること(※1)。
分娩を希望するがん患者さんの妊よう性とがん治療をどう両立させるかという課題が顕在化しているんです。
この課題に直面しているのは、既婚の女性ばかりではありません。がんに罹患したときには未婚で、パートナーもいない。でも、いずれは子どもを持ちたいという方もいます。
ご相談者さんも独身なら、これは切実かつ身近な問題だと思います。
妊よう性の温存について担当の医師に確認しよう
では、がん治療を行いつつ、妊よう性を温存するためにはどうしたら良いのでしょうか。
そもそも、がん治療では、妊娠に必要な生殖機能にかかわる臓器を手術で摘出したり、薬物療法や放射線療法が影響を与えたりする可能性があるのです。妊よう性に対する影響は、一時的なものと永久的なものがあります。
例えば、女性なら、手術で両側の卵巣や子宮を摘出してしまうと、妊娠は永久にできなくなりますよね。
そこで、分娩を望む場合は、がん告知後に治療を始める前に、これから受ける治療が自分の生殖機能にどのような影響があり、妊よう性の温存が可能なのか、具体的にどのような方法があるのかを担当の医師に確認しましょう。
抗がん剤の影響や、卵子や卵巣、受精卵の凍結といった方法のメリット・デメリットなどを早い段階で確認し、安全性や有効性などを慎重に検討してください。

ただし、妊よう性の温存のためには、生殖医療の専門医の判断も仰ぐ必要があります。必ずしも担当医が生殖医療についてよく知っているとは限りません。将来的な妊娠を想定した治療方法を検討してもらえる病院を探しましょう。
日本の場合、妊よう性の温存については患者も医療者も認識が十分とはいえません。手遅れになる前に行動してくださいね。
費用は公的な医療保険の適用外、助成金制度もあり
ご相談者さんが気になっている費用については、率直に申し上げると、かなりの負担がかかります。
だいたいの費用の目安としては以下の通りです。女性は、既婚あるいはパートナーがいる場合の「受精卵凍結」、独身あるいはパートナーがいない場合の「卵子凍結」、男性は「精子凍結」などがあります。月経前やがん治療の開始を遅らせることができない、卵巣機能が低下している場合は「卵巣凍結」などを行います。
費用は医療機関によって異なりますので、直接確認をしてみてください。
これらはいずれも保険適用外の自由診療の扱いになるため、非常に高額になるのです。
· カウンセリング料:初回5,000円、再診2,000円
· 受精卵凍結:約40~80万円+移植時25~35万円
· 卵子凍結:約30~70万円+移植時35~45万円
· 卵巣組織凍結:約55~100万円+移植時55~100万円
· 精子凍結:約5万円
· 凍結保存した場合の更新料:約2~10万円/年
実際に、これらの治療を受けた患者さんがどれくらい負担しているのか?
若年性乳がんサポートコミュニティ「Pink Ring」が、2017年に満20歳~50歳の男女約500人を対象に行った「がん治療後に子どもを持つ可能性を残す 思春期・若年成人がん患者に対するがん・生殖医療に要する時間および経済的負担に関する実態調査」の結果を見てみましょう。
妊よう性温存を実施した患者は全体の16.8%。行った方法としては、受精卵凍結47.0%、卵子凍結33.7%と、その2つで全体の約8割を占めています。
妊よう性温存に要した費用については「50万円未満だった」と答えた方が約50%。「50万円以上支払った」という方が約46%でした。
しかも、これはがん治療とは別にかかる費用です。子どもを持つ可能性を残すためとはいえ、重い負担であることは間違いありません。
ただ、不妊治療については、2022年4月以降、タイミング法や人工授精などの「一般不妊治療」や、体外受精・顕微授精などの「生殖補助医療」が保険適用となっています。
しかし、保険適用の対象となるのは、既婚者(事実婚含む)のみです。未婚のがん患者さんは適用が受けられません。
そこで、AYA世代※等のがん患者さんの経済的負担を経験する目的で、国の小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業が開始され、2022年4月から、体外受精などの生殖補助医療が助成対象となっています。
※Adolescent&Young Adult(思春期・若年成人)の略で、15歳から39歳の患者さんのこと。
それぞれ、治療法や助成上限額、回数などは決まっていますが、自治体によって異なる場合もありますので、お住まいの自治体に確認してみてください。

知識があったから乳がんでも子どもを産めた

最後に、妊娠中に初期の乳がんが見つかった女性の話を紹介させてください。
彼女は当初、産婦人科医に「がん治療を優先させるべきです。子どもは諦めてください」と言われたそうです。
しかし、以前、がんと妊よう性の特集をテレビで見たことを思い出し、夫がインターネットで、治療しながらも子どもを産める実績のある病院を探して、すぐにそちらに転院。
乳房温存手術や抗がん剤治療を受けながらも、妊娠を継続することができました。
その結果、無事に女児が生まれました。出産後もすぐに抗がん剤治療を始めなくてはならず、通院や副作用で、子育てと治療の両立は大変です。
でも、夫やご両親の協力を得て、充実した日々を送っておられるとのことです。
がんのステージや病状にもよりますが、がん治療を受けながら子どもを産める可能性があることは、ぜひ知っておいていただきたいと思います。
※1 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)
<クレジット>
取材/ライフネットジャーナル オンライン 編集部
文/三田村蕗子
撮影/村上悦子
<プロフィール>
黒田尚子(くろだ・なおこ) 1969年富山生まれ。立命館大学卒業後、1992年(株)日本総合研究所に入社。1998年、独立系FPに転身。現在は、各種セミナーや講演・講座の講師、新聞・書籍・雑誌・ウェブサイトへの執筆、個人相談等で幅広く活躍。2009年12月に乳がんに罹患し、以来「メディカルファイナンス」を大テーマとし、病気に対する経済的備えの重要性を訴える活動も行っている。CFP® 1級ファイナンシャルプランニング技能士、CNJ認定 乳がん体験者コーディネーター、消費生活専門相談員資格を保有。
●黒田尚子FP オフィス
※こちらの記事は、ライフネット生命のオウンドメディアに過去掲載されていたものの再掲です。