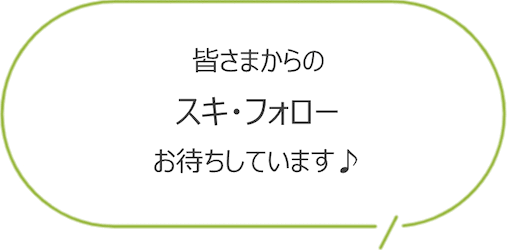学生も実は他人事じゃない!? 扶養から外れると起きる家族の収入減少―「年収の壁」問題を解説
アルバイトやパートなど雇用形態に関係なく、収入が一定以上になると、税金の発生や社会保険への加入といった変化が起こります。この収入に関する条件は「年収の壁」と呼ばれています。
特にアルバイトをしている学生さんで、親や配偶者など(以下、単に「親」と記載します)の扶養に入っている方たちは、収入が一定以上になるとその扶養から外れてしまうため、この壁を超えないようにと働き控えをしている人もいるとされています。
今回は、社会保障制度のプロである社会保険労務士としても活躍するファイナンシャル・プランナーの中村先生に、学生もぶつかるかもしれない「年収の壁」事例について伺っていきます。
<前編はこちら>
※専門的な用語をできるだけわかりやすい用語に置き換えています。また、詳細な説明を省略しているため、すべての要件などまで触れていません。
※この記事では、2025年1月時点の制度に基づいた情報を掲載しています。
学生でも収入が増えて扶養から抜けてしまうと親の収入が減ってしまうことも
―ここまで「年収の壁」の概要をご説明いただきましたが、若い世代でも注意しないといけないケースなどもありますよね。ここからは中村先生が実際に見られた事例や、その対処法を伺えればと思います。
中村:まだ学生の場合でも、アルバイトを少し頑張ったら扶養から抜けてしまうケースがあります。そうすると子どもは収入が増えても、親御さんの収入が減るというショックを受ける可能性があります。

具体的にはアルバイトの収入が103万円を超えるケースです。
親の扶養から外れると、親の支払う税金が多くなってしまう
子どもの収入が103万円以内であれば、親の扶養に入ることで税金を軽減できる「扶養控除」という制度があります。親の税金の計算をするときに、38万円(19歳~23歳未満は63万円。以下、63万円)が収入から控除されます。

控除という単語が出てきたら、税金的にいいことがあると思っておいてください。そして控除がなくなるということは、税金的にデメリットが出てくるということです。
しかし子どもの収入が103万円を超えた場合、子どもは親の扶養から抜けないといけなくなります。そうすると親が受けていた38万円(63万円)の控除がなくなり、前より税金の支払いも多くなる。そうして、家計の負担が大きくなってしまう可能性があるのです。
そうなってしまうと親御さんもびっくりしてしまうでしょうから、アルバイトをしている学生さんは月の収入を確認して、もしかしたらというときには親御さんと相談してくださいね。特に一人暮らしをしていて、かつ親の扶養に入っているケースは注意しましょう。
―もし扶養から外れると、次の年からもずっと扶養に入れないのでしょうか?
中村:いえ、扶養に入れるかはその年の収入で判断されますので、また子どもの収入が一定未満になれば扶養に入りなおすこともできます。一度扶養から外れてしまっても、その点は安心してください。
親が会社からの家族手当を受け取れなくなることも
中村:企業の中には、扶養に入れている人がいると支給される「家族手当」を社員へ支給している企業もあります。
【民間企業における「家族手当」の支給状況】

家族手当制度がある会社は実に約75%。そして、扶養に入っている人の収入に制限がある会社がほとんどです。ここでは配偶者となっていますが、子どもの場合も同様です。
収入の制限については、103万円を「壁」としているところが4割。子どもが103万円の壁を超えて扶養から外れると、控除がなくなる上に会社からの扶養手当も受け取れなくなる、家計へのダブルパンチが発生するかもしれないのです。
例えば月々5,000円であれば、年間で6万円受け取れていたものがなくなることになるので、親に会社から扶養手当が出ているかを確認しましょう。
―夏休みや冬休みにアルバイト入れすぎてやばい~、なんて学生時代に話していたのを思い出しました。
中村:扶養から外れるかどうかの計算は毎年1月から12月の収入で決まります。夏に頑張りすぎて翌月払いの給与を見たら9月までにだいぶ稼いでしまった場合、10月以降の働き方によっては親の扶養から外れるくらいの収入になるかもしれませんね。
ただ、扶養から外れないように働き方を調整すると自分の収入が減るわけで、やりたいことができないなど可能性の芽を摘むことになるかもしれません。働けるのでしたら、できる範囲で働いてもいいんじゃないかとは思います。
とはいえアルバイトはしているけれどお金を家に入れていないというのであれば、扶養手当がなくなると親御さんには少なくない打撃になりますから、家族会議的なことはしておいて、お互い状況を把握しておけるようにしましょう。会議の結果どうするかは各ご家庭の判断ということになります。
親の扶養に入る「子ども」でも気を付けないといけない年金のあれこれ
中村:年金というとお年寄りのものというイメージもあるかもしれませんが、実は子どもの立場でも年金で注意しなくてはいけないポイントもあります。
「扶養」と一言にいっても、税金の扶養と社会保険の扶養とが存在します。そして社会保険の扶養はさらに、健康保険の扶養と年金の扶養という切り分けがあります。
20歳を過ぎたら基本的に年金制度上は一人前の大人として扱われます。そのため、20歳を超えた子どもは健康保険上では扶養に入っていたとしても、年金制度上では扶養に入れません。
たまに、成人して就職した子どもが会社を辞め、親の扶養に再度入ることになったケースの相談を受けます。「第3号被保険者」という国民年金上の扶養制度もありますが、それは配偶者しか使えない制度です。扶養に入った子どもであっても、国民年金保険料の納付は自分で行わなくてはいけません。
社会保険で親の扶養に入ることは、おおむね何歳でもできますが、年金だけはできません。「年金の納付書が届いたけれど、親の扶養に入っているから無視していいよね」と、無視してしまうことのないよう気を付けてくださいね。
―年金でいうと、学生納付特例制度(※)を利用していた場合も気を付けないといけませんよね。猶予を受けられることは知っていても、10年以内に納付しなくてはいけないことを知らず、10年を超えてからそのことを知った人もいると思います。これはどれくらいピンチな状態なのでしょうか。
※学生納付特例制度:申請により在学中の国民年金の保険料の納付が猶予される制度のこと。
中村:学生納付特例制度での猶予を受ける手続きのときに、チラシなどを見て目に入っていても、数年経った頃には忘れてしまいますよね。
まず安心してほしいのは、猶予を受けた期間が10年や20年もあったら穴埋めはかなり大変ですが、20歳からの2年や3年などであれば、ある程度の穴埋めはできます。例えば60歳以降も会社勤めをするとか、60歳以降に3年分の保険料を払うなど、年金保険料納付のゴール前でも辻褄を合わせることができると覚えておいてください。
―今はニュースでも「年収の壁」についての話題で持ちきりですが、学生の方にとっても他人事ではない話だなと改めて感じました。中村先生、ありがとうございました。
<クレジット>
取材/ライフネット生命公式note編集部
文/年永亜美(ライフネット生命公式note編集部)
<プロフィール>
中村薫(なかむら・かおる)1990年より都内の信用金庫に勤務。退職後数ヶ月間米国に留学し、航空機操縦士(パイロット)ライセンスを取得。訓練中に腰を痛め米国で病院へ行き、帰国後日本の保険会社から保険金を受け取る。この経験から保険の有用性を感じ1993年に大手生命保険会社の営業職員となり、1995年より損害保険の代理店業務を開始。1996年にAFP、翌年にCFP®を取得し、1997年にFPとして独立開業。2015年に社会保険労務士業務開始。キャリア・コンサルタント、終活カウンセラー、宅地建物取引士の有資格者でもある。
●なごみFP・社労士事務所